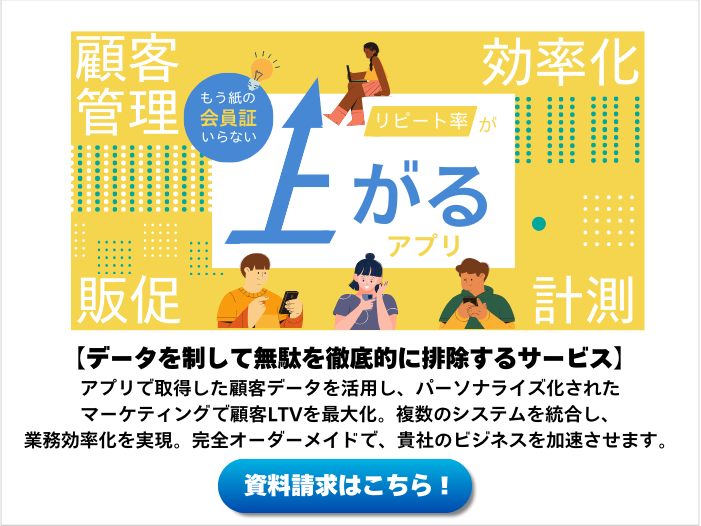インフレや原材料費の高騰、人件費の増加、さらに為替変動……最近は価格の見直しを迫られている飲食店が多いですよね。でも『値上げすべき?それとも現状維持?』と、迷っている経営者の方も多いのではないでしょうか。松屋・松のやが深夜料金を導入したというニュース、聞いたことはありますか?この事例、価格設定について考えるための良いヒントになりそうです!本記事では、松屋・松のやの深夜料金の事例をもとに、価格決定に必要な心構えについて解説していきます。
記事の信憑性
この記事で提案した考え方や具体的な行動は、インバウンド需要にも応える「ExCafe」や「麵処むらじ」など、多くの成功事例を持つインデングループの実績に基づいています。創業から25年、変化の激しい市場で成功と失敗を繰り返しながら得た経験が、このノウハウの信頼性を支えています。
~目次~
1.松屋・松のやが導入した深夜料金の概要
2.不安定な世の中で価格を決定するために大切な一つの心構え
1. 松屋・松のやが導入した深夜料金の概要
松屋と松のやは2024年に深夜料金を導入しました。対象時間は22時から翌5時で、この時間帯に注文する場合、各商品の価格に7%前後の追加料金が加算されます。
松屋・松のやが深夜料金を導入した理由は、以下の通りです。
・深夜営業にかかるコスト増加:深夜帯は人件費が高くなりがちです。なぜなら、深夜に働きたい人が少ないため、割増賃金を支払う必要があります。
・原材料費の高騰:世界的なインフレや円安によって、食材の仕入れコストが増加しています。
・光熱費の上昇:深夜に営業することで光熱費も増えます。
このような背景から、深夜帯の営業を続けるためには、コストを価格に転嫁し、原資を確保する必要があったのです。
深夜料金が導入されると、「仕方ない」「理解できる」といった声がある一方で、「値上げは残念」という意見も見られました。成功のカギは、顧客が納得できる理由と価格を明確にし、理解を得ることです。
2. 不安定な世の中で価格を決定するために大切な一つの心構え
結論、「定数を動かさない」ことです。コストには「定数」と「変数」が存在し、これを見極めて無駄な部分だけを削減するのが賢明です。
定数:経営努力では動かせないコスト。例えば、深夜帯の人件費が高くなるのは、働き手が少ないという「世の理」だからです。これを無理に下げようとしても、サービスの質や従業員満足度が低下し、逆に損失を生む可能性があります。
変数:努力次第で削減できる無駄なコスト。例えば、過剰な在庫、不要な設備投資、効率の悪い業務フローなどです。
松屋・松のやが深夜料金を設定したのは、「深夜の人件費は定数であり、動かせない」と判断したからです。無理にこのコストを削減するのではなく、深夜に追加料金を設定することで、必要なコストをまかなう手段を選びました。 価格を見直す際、最優先すべきはデータに基づく分析です。当たり前のように思えますが、現場では感覚や勘に頼ってしまいがちです。データ分析によって、次のような視点を得ることができます。
1.定数と変数の明確化
何が動かせないコストで、何が無駄なコストなのかを正確に把握できます
2.最適な価格設定
顧客が許容できる価格帯をデータで検証し、適正な価格を導き出せます。
3.効率的なコスト削減
どの部分のコストを削減すべきかを数値で示せるため、無駄な努力を防げます。
「でも、データ分析って難しそう……」と感じる方も多いかもしれません。そんな時は、専門サービスを外注するのも一つの手です。無料で資料請求や相談ができるサービスもあるので、気軽に活用してみましょう!
まとめ
価格を引き上げるべきかどうかの判断は、決して簡単ではありません。松屋・松のやの深夜料金導入は、コストの「定数」と「変数」を見極めた上での決断でした。
1.定数を動かさない:動かせないコストに無理に手を加えるのではなく、変数(無駄なコスト)を削減することを優先する。
2.データに基づく判断:定数と変数を正確に見極めるためには、データ分析が不可欠。
3.顧客の理解を得る価格設定:顧客が納得する理由と価格を明確に伝え、信頼関係を保つことが成功のカギ。
ビジネスにおいて「価格設定」は避けて通れないテーマです。データを基にした冷静な判断と、動かせないコストへの理解が、これからの不安定な時代を生き抜くための重要な心構えとなるでしょう。